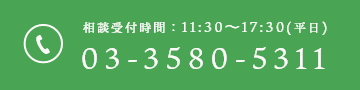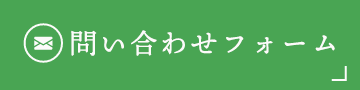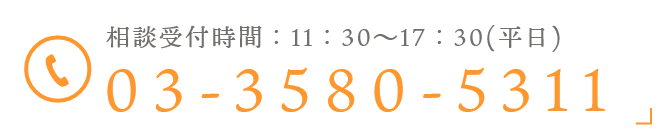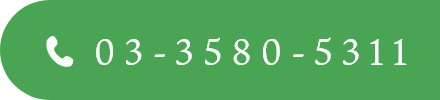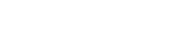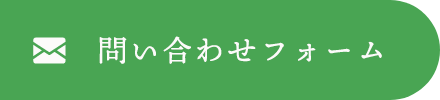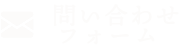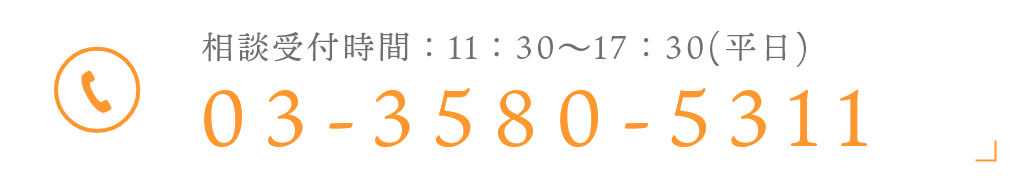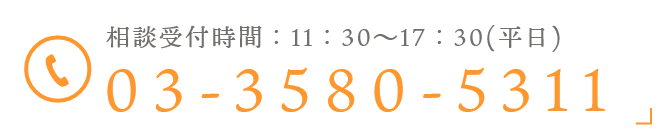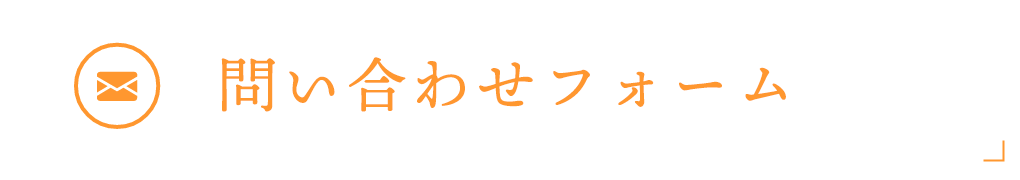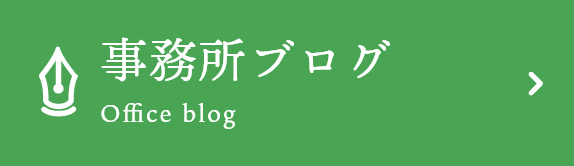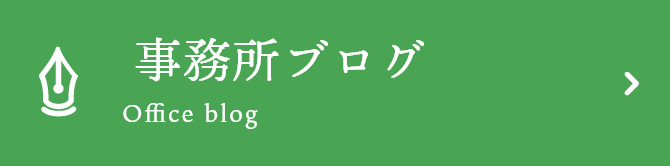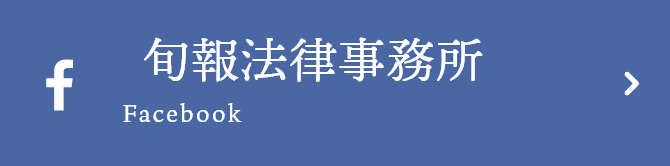労災
こんなお悩みありませんか。

- 過重な労働でうつ病になり、会社に行くことができない
- 労働災害なのに会社が労働災害として認めず、私傷病扱いされている
- 休職期間が終わると言われているが、本来労災なのではないか
- 出勤途中に転倒してケガをしたが、労働災害ではないかと思う
- 腰痛や腱鞘炎だが、労働災害ではないかと思う
弁護士に依頼するメリット
労働災害で怪我や病気、死亡した場合、ご本人やご家族は労災保険給付の申請と損害賠償の請求ができます。
しかし、会社が労災申請に協力しない場合や、賠償責任を認めない場合などもあります。当事務所の弁護士には労災の証拠を集めるノウハウがあり、労災認定を勝ち取ってきた実績がございます。また、労災請求と損害賠償請求のどちらを先にするべきか、などのアドバイスも可能です。
労災にあったとき、どんな請求ができるの?
労災事案の場合、ご本人やご遺族は、⑴労働基準監督署に対する労災保険給付の申請(労災申請)と、⑵会社に対する損害賠償請求 を行うことができます。
労災申請
労災保険は、業務上の災害、または、通勤災害について、被災された労働者やその遺族に保険給付を行うものです。
労働者を1人でも使用する事業所(5人未満を雇用する農林水産業を除く)であれば、労働者は保険の対象になります。
会社が労災保険料を支払っていない場合でも、労災保険から保険給付は受けられますので、ご安心ください。
業務上の災害と認められるには、①ケガや労災補償の対象となる病気の発症、②業務遂行性・業務起因性、つまりケガや病気の発症が業務(仕事)を原因としていること、が必要となります。
作業の準備や後片付け中の事故によるケガなど、業務に付随することを行っているときの災害も業務上の災害として認められることがあります。
通勤災害と認められるには、労災保険法で保護される「通勤」(自宅と会社の間の往復など)であることが必要です。
共稼ぎの夫婦が子どもを保育園等に預けてから会社に向かう場合も「通勤」にあたるとされていますが、他方、帰宅途中に飲食店で長時間にわたって私的に飲食した後に自宅に向かう場合には「通勤」にはあたらないとみられます。
損害賠償請求
また、会社に、①安全配慮義務(労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務)違反の責任(民法415条)か、②不法行為責任(民法709条、715条、717条)がある場合には、会社に対する損害賠償請求をすることができます。
労災保険による給付には、慰謝料は含まれず、休業損害も収入の6割にとどまるなど実際に発生した損害のすべてがカバーされてはいません。このため、一般には、労災申請だけでなく、会社に対する損害賠償請求を行う事案が多いです(ただし、労災保険から給付された金額については差し引くこととなります)。
いずれの請求を行うのか、どの順序で行うか等については専門的な判断が必要となります。当事務所には、多くの労災事件を取り扱った経験とノウハウがありますので、ぜひご相談ください。
精神障害事案のポイントは?
最近では、自殺(自死)にまで至らなくても、仕事による過労・ストレスによる精神障害が増えています。
厚生労働省は、平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定め、その後改定を経つつも、これに基づいて労災認定を行っています。
精神障害事案で労災認定のハードルとなるのが業務起因性です。
業務起因性は、上記認定基準に定められた長時間労働、ひどいいじめ・ハラスメント等の出来事の有無により、判断されます。
労災認定がされるかどうかの基準や指針については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
弁護士に依頼した方がいいの?
資料の収集と就労実態の解明
労災認定の基準を満たすと言えるためには、労働者の働いていた具体的な状況(業務内容や労働時間など)、その心理的負荷の大きさ、発症との因果関係などについて、関係者からの事情聴取や証拠保全手続きなども行いながらできるだけ多くの資料を集め、また、それらを分かりやすく整理して立証することが必要です。
専門家による主張・立証
労災が認められるためには、業務が過重であったことなどについて詳細な主張・立証が必要になることがあります。
たとえば、精神障害については、労災と認定されるための条件である「業務による強い心理的負荷が認められること」について「業務による心理的負荷評価表」により総合評価することになります。上記のとおり、これに当たる事実があるかどうかを多くの証拠を集め、その中から探し出し、どの事実がそれに当たるかを吟味・整理して主張・立証しなければなりません。
損害賠償請求でも
こうしたことは、会社(使用者)に対する損害賠償請求でも同じです。損害賠償請求では、さらに会社(使用者)の責任(故意・過失)についても、基本的に労働者側で主張立証することが必要になります。事故発生からあまり時間の経っていない段階から、たくさんの資料を収集して、実態を解明して、十分な主張立証を行っておくことが重要です。
こうしたことから、確実に労災認定を勝ち取ったり会社に損害賠償をさせたりするには、労災事案についての基準や指針などの知識だけでなく、証拠集めも含めて経験やノウハウのある弁護士に依頼した方がいいでしょう。
旬報法律事務所の取組み実績は?
旬報法律事務所では、1954年の創立以来、多くの労災事件に取り組んできました。
過労死・過労自殺事件
ここ最近では、以下のような事案があります。
・出向後・過労自殺事件(配置転換、長時間労働、2012年労災認定)
・若年管理職の心筋梗塞事件(長時間労働、不規則勤務、2014年労災認定、2014年訴訟外での和解成立)
・営業職員の脳梗塞事件(2010年労災認定、2015年訴訟上の和解成立)
・トラックドライバーの脳内出血事件(2014年労災認定)
・裁量労働制のアナリストの心室細動事件(2015年労災認定)
・メディア職員の心臓突然死事件(2015年労災認定、2015年民事調停にて和解成立)
・NHK女性記者の心停止事件(2015年労災認定)
・物流管理職の過労自死事案(長時間労働、2015年労災認定)
・情報通信企業マネージャーの過労自殺事件(2016年労災認定)
・SEの過労自死(達成困難なノルマ、2017年労災認定)
・電通新入女性社員過労自殺事件(2016年労災認定)
・営業補佐職の致死性不整脈事案(長時間労働、2017年労災認定)
・執行役員の大動脈解離事案(長時間労働、2018年労災認定)
・ドライバー職の不整脈事案(長時間労働、兼業・副業事案、2019年労災認定)
・警備会社の管理職の過労自死(長時間労働、連続勤務、2019年労災認定)
・ラーメン屋店長の過労自死(長時間労働等により脳疾患発症後、後遺症を苦に自死、2019年労災認定)
・財務経理担当者の過労死(脳心臓疾患・長時間労働、2019年労災認定)
・トラックドライバーの過労死(脳心臓疾患・長時間労働、2020年労災認定)
・不動産営業職員の過労自死(達成困難なノルマ等、2020年労災認定)
・支所長の過労自死事案(長時間労働、仕事量・仕事内容の変化、2020年労災認定)
・店舗責任者の過労自死事案(極度の長時間労働、2020年労災認定)
・電子機器販売店社員の過労自死(長時間労働、強い指導・叱責、2022年労災認定)
・長距離トラックドライバーの過労死(脳疾患・長時間労働、2022年労災認定)
・管理職のくも膜下出血事案(長時間労働、連続勤務、移動、出張、2023年労災認定)
・営業職員の過労自死事案(長時間労働、トラブル、2023年労災認定)
その他の労災事案
また、上記のような過労死事案以外でも、長時間労働による精神疾患の事案などで多くの労災認定を勝ち取っています。
例えば、以下のような事案があります。
・システムエンジニアの精神疾患(長時間労働、2014年)
・トラックドライバーの脳疾患(長時間労働、2016年)
・営業社員の脳疾患(長時間労働、2017年)
・トラックドライバーの長時間労働による精神疾患事案(2019年労災認定)
・訪問介護士の長時間労働による精神疾患事案(2020年労災認定)
・介護施設長の精神疾患発症(長時間労働、違法行為の強要、強権的な言動、2020年労災認定)
・警備員の精神疾患事案(長時間労働、仕事量・仕事内容の変化、2020年労災認定)
・士業従事者の精神疾患事案(長時間労働、過大なノルマ、仕事量・仕事内容の変化、2020年労災認定)
旬報法律事務所の弁護士は、過労死弁護団や日本労働弁護団に加入して、最新の労災認定の状況を把握するなど、ご相談者様・ご依頼者様のお役に立てるよう日々研鑽を積んでいます。