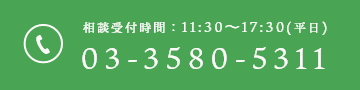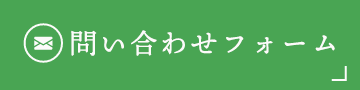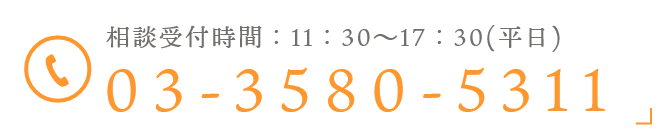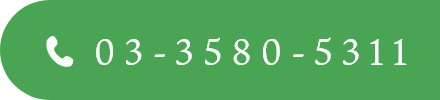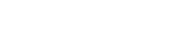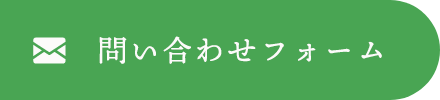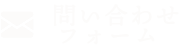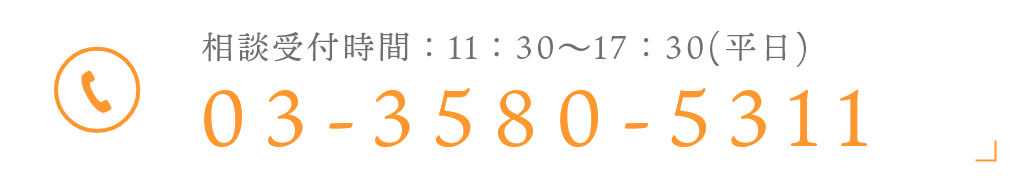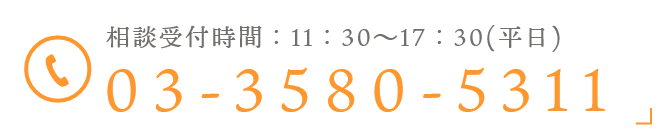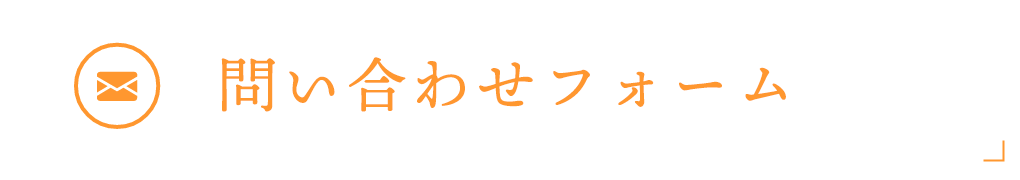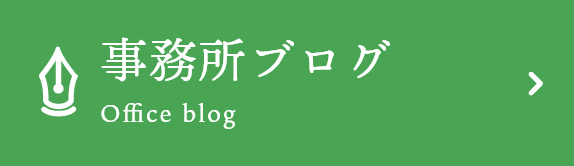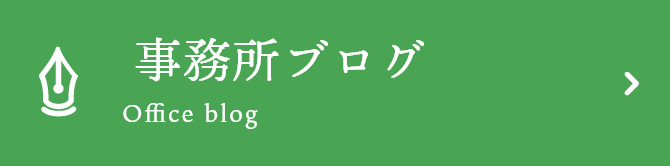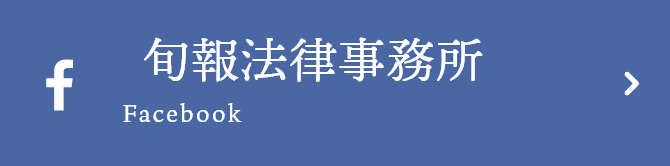退職勧奨・PIP
こんなお悩みありませんか?

- 会社の業績が悪いから退職してほしいと言われている
- 退職を拒否しているのに、繰り返し退職を求められる
- 突然PIPを言い渡された
- 言い渡されたPIPの内容や目標が曖昧
- PIPの結果、解雇され、または降格・減給された
退職勧奨
「退職勧奨」とは、使用者(会社)が労働者に対して、退職の意思表示をするようお願いすることです。したがって、労働者が退職勧奨に応じて、退職の意思表示をしなければ、労働契約終了の効果は生じません。労働者に退職勧奨に応じる義務はないので、退職勧奨を受けているだけであれば、辞める必要はありません。
PIPとは
PIPとは、Performance Improvement PlanまたはPerformance Improvement Programの略で、業績改善プランまたは業績改善プログラムのことを言い、会社が労働者に対して業績改善や成績向上のために目標や計画を作成させて行う業績改善指導の手法です。
PIPは、本来は業績不良な労働者に対して業績の改善を目的として行われるものですが、労働者を退職させ、または解雇する手段として用いられたり、降格・減給の手段として用いられることも少なくありません。
退職勧奨に対して弁護士は何ができるか
退職勧奨に応じるか否かは、労働者の完全な「自由」です。まず、この点をしっかりと押さえておきましょう。「労働者が退職勧奨を断ったら、会社は法律上、労働者を解雇できる」と誤解している人もいますが、そのようなことはありません。但し、会社が倒産危機にあるような場合や何らかの解雇理由が存在する場合などには、退職勧奨を断った後、解雇や配置転換等の措置を取られることがあるので、そのような事態も見越した対応を考えておくことが重要です。
会社が退職勧奨を行うことは法律で禁止されていませんが、労働者が明確に退職を断っているにもかかわらず、執拗に退職勧奨が繰り返されたり、長時間にわたり脅迫的な言動を伴うなど、退職勧奨の態様が許される限度を逸脱する場合には、退職「強要」として違法となり、損害賠償の対象となる場合があります(強要にあたるかどうかの判断は事案により異なりますので、弁護士にご相談ください)。
したがって、ご相談者様が会社に対して「退職するつもりはない」と伝えているにもかかわらず、会社が引き続き退職勧奨をしてくる場合には、弁護士が、会社に対し、これ以上の退職勧奨をやめるよう通知し、交渉することが可能です。
また、ご相談者様の意向が、「退職に応じてもよいが、急に職を失うことに対する何らかの補償をしてほしい」ということであれば、弁護士がご相談者様に代わって、会社との間で補償内容(退職条件)について交渉することが考えられます。
いずれにせよ、退職勧奨に対する対応は、ケースバイケースであり、労働者の置かれた具体的な状況や会社の意向によっても微妙な判断を要するため、経験豊富な弁護士に相談し、アドバイスを得ることが大切です。
PIPに対して弁護士は何ができるか
PIPを告げられたら、まずはご相談ください。
これから行われようとしているPIPに対して弁護士が介入する場合には、会社に対して内容証明郵便を送り、PIPを実施せず、撤回するよう求めるのが一般的です。また、併せて、事案に応じて、内容証明郵便では、PIPが実施されるような業績不良がないこと、会社が指摘する業績不良とPIPの内容が関係していないこと、PIPの達成目標があいまいであることなどを指摘することも行います。
PIPが実施される場合、今後の処遇などに強い不安を覚えることもよくあります。弁護士から、アドバイスを受けながらより良い解決を目指すことで、落ち着いて対応することも可能になります。
既にPIPが開始されている場合でも、弁護士が介入して上記の指摘を行い、PIPを止めるよう求めたり、PIPの結果による退職勧奨や解雇などを行わないよう求めることになります。
PIPが終了して解雇や降格・減給などの処分が行われた場合には、これらの処分に対する法的措置を検討し、または処分の違法性を指摘してその撤回を求めるなどの対応も必要となります。これにあたっては、処分の有効性に関する様々な要素を検討する必要があり、十分な知識や経験がなければ適切に対応することができません。
当事務所では、ご相談者様の訴えに耳を傾け、不安を軽減しつつより良い解決に向けて様々な要素を検討し、豊富な知識と労働事件取扱経験に基づいてアドバイスを行い、対応しています。
相談事例 退職勧奨のケース
ご相談内容
中途採用で専門職として入社しました。まだ2か月しか働いていないのに、社長から、専門職として期待していた能力が足りていないので辞めてもらいたいと言われています。退職届にサインをすれば退職金を支払うが、サインしなければ解雇すると言われています。私は退職しなければならないのでしょうか。
弁護士の見解
会社はあなたに、退職届にサインして退職するようお願いしているだけなので、解雇ではなく退職勧奨です。退職勧奨に応じるか否かは労働者の自由なので、退職勧奨に応じて退職する必要はありません。
退職勧奨に応じない場合、会社はあなたを解雇するかもしれませんが、解雇は「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合でなければ、その解雇は無効となります(労働契約法16条)。
対応について
退職勧奨に応じて退職する必要はないので、会社で働き続けたいのであれば、弁護士から会社に対してこれ以上退職勧奨をしないよう通知することができます。
その場合、会社が解雇をしてきた場合に解雇が有効となるか検討しておく必要があります。解雇が有効となるかは、会社が何をもって「専門職として期待していた能力が足りていない」と言っているのかを明らかにして、客観的事実に基づいて判断する必要があります。
また、会社で働き続けたくない場合でも、弁護士を通じて退職金の上乗せなど、退職条件の交渉をすることもできますので、まずはご相談下さい。
当事務所が扱った解決事例(PIPのケース)
以下は、当事務所で取り扱った具体的事例です。ただ、解決方法や水準は事案や相手の対応によって異なりますので、ご自身の事案についてどのような解決ができそうか、詳細は弁護士にお気軽にご相談ください。
ケース1
チームリーダーを務めるAさんは、部下に対して複数のパワーハラスメントを行ったことを理由に、コミュニケーション能力を改善する必要があるとしてPIPの実施を告げられました。
Aさんは直ちに弁護士に相談し、弁護士から内容証明郵便を送り、PIPを実施せず撤回するよう求めました。その中では、パワーハラスメントの一部は既に解決済みであり、その他のものは事実無根であること、パワーハラスメントがあったとされる年も含めてこの間の人事評価は対人関係項目も総合評価もいずれも高評価であったこと、会社の定める実施要件を満たさないこと、PIPの目標があいまいで恣意的な評価が可能であること等を指摘しました。
内容証明郵便を送った後、会社側と数度の交渉を行った結果、PIPを実施させず、結局ご相談いただいてから約4か月でPIPを撤回させることができました。
ケース2
マネージャーとして中途採用されたBさんは、それまで高評価を受け、順調に昇給してきていたにもかかわらず、突如としてPIPが実施され、目標不達成として合計4回のPIPが実施されました。
そこで、Bさんは弁護士に依頼して 成績不良がないことやPIPの目標とされている内容がBさんの業務と無関係であること、会社側の安全配慮義務違反などを主張して会社と交渉しました。
その結果、和解成立から約3か月後に退職すること、退職までは就労が免除されつつ賃金が支払われること、退職時に割増退職金として約2年分の年収を支払うことなどを内容として解決することができました。