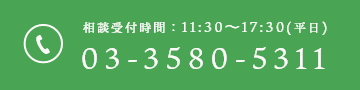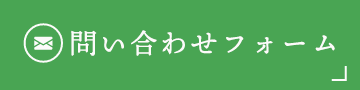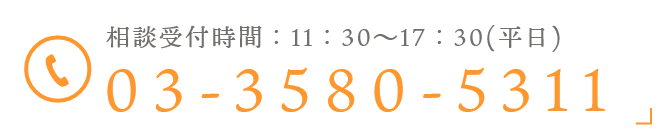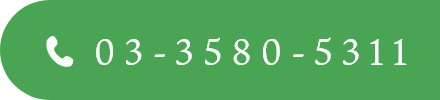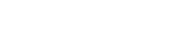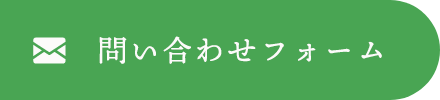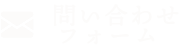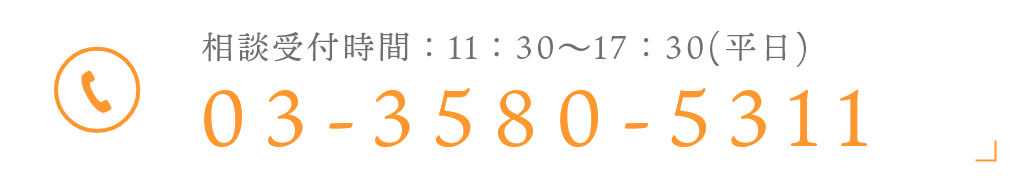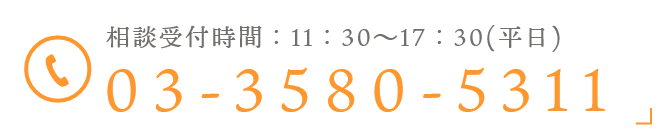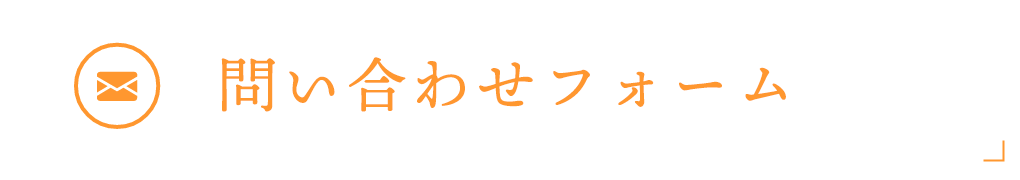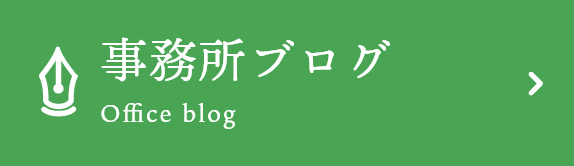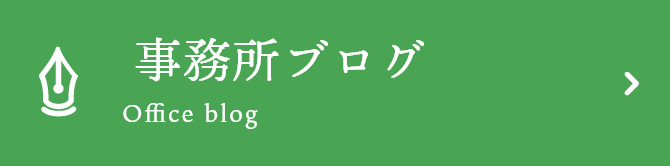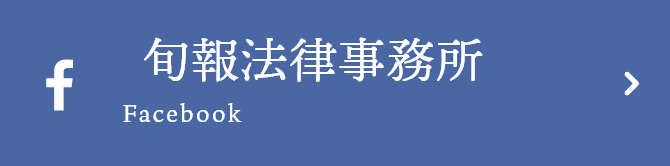賃金・退職金
こんなお悩みありませんか。
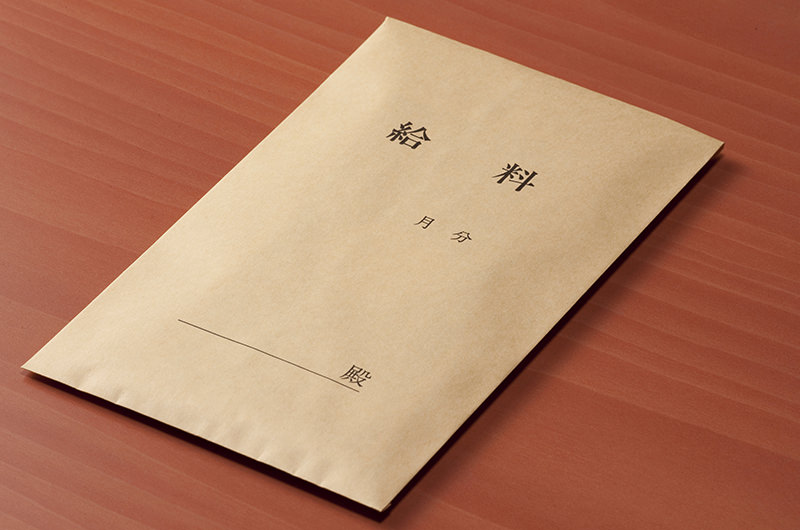
- 会社が一方的に賃金を引き下げてしまった
- 会社が賃金の引き下げを提案し、これに同意するよう強要してくる
- 一時的に賃金を下げるが元に戻す、と言われていたのに戻してくれない
- 会社都合での退職なのに、自己都合退職として退職金を低く算定された
- 懲戒解雇で退職金をもらえなかった
- 賃金が未払いのまま会社が倒産してしまった
- 退職金があると聞いていたが規程を見せてもらえない
弁護士に依頼するメリット
賃金の問題は、個人で会社と相対するのは大変ですし、会社の言い分が正しいのかを判断できないことも多いでしょう。また、会社の経営状態が悪いということを理由に賃金を支払ってくれない会社もあります。
このような場合でも、弁護士にご依頼いただくことで、会社に対して法律や会社の規程に基づいた賃金や退職金の請求をすることができます。会社が賃金を任意に支払わないときには、会社に残っている財産を差し押さえるなどして賃金の回収をすることが可能です。
相談事例1 賃金減額を求められたケース
ご相談内容
「会社の景気が悪いから」と賃金減額を迫られ、断れませんでした。もう、どうにもならないのでしょうか。
弁護士の見解
労働契約も契約なので、合意によって契約内容を変えることは不可能ではありません。したがって、合意によって賃金を減額することも可能な場合があります。
しかし、労働者と使用者との間の力関係を考慮すると、労働者による合意が真に自由な意思に基づくものであるか否かは慎重に判断されるべきです。減額する理由もないのに減額に応じてしまった場合や、何らかの理由があったとしてもあまりに大きな減額幅である場合などは、賃金減額を明確に断らなかったとしても、有効な承諾(同意)を行ったとはいえないと判断される可能性があります。
また、会社から十分な説明がなく労働者が誤解したまま同意してしまった場合や、会社から減額に応じるよう強く迫られて本意ではないにもかかわらず同意を示してしまったなどの場合も、賃金減額が無効であることなどを主張することが考えられます。
さらに、就業規則(に基づく賃金規程)が定める賃金水準を下回るような減額は許されません(労働契約法12条)ので、その場合にも減額を争うことが可能です。
対応について
賃金減額をされるに至った経緯などをお聞きして、減額の無効などを主張できないか検討いたします。上記のように、たとえ減額を断れなかったとしても、減額分を取り戻す余地がありますので、ぜひ諦めずにご相談ください。
相談事例2 正当な理由がなく賃金が支払われないケース
ご相談内容
会社が何の理由もなく賃金の一部を支払ってくれません。これは違法ではないのでしょうか?
また、速やかに不払いとなっている賃金を会社に支払わせることはできませんか?
弁護士の見解
労働基準法24条には「賃金全額払いの原則」というものが定められています。理由のない賃金の不払いは当然に同条違反です。
会社が任意に支払わない場合には、訴訟や労働審判を起こすこともできますし、賃金の不払いについて明らかな証拠があれば、「先取特権」という権利を利用して、会社の財産を差し押さえて賃金を回収することができます。
対応について
会社を相手に個人で対応すると、証拠を隠されたり、さらに会社に対して賃金の支払いを求めたことを理由に不当な処遇を受けたりする可能性もあります。様々な状況に合わせて経験豊富な弁護士が対応いたしますので、ぜひご相談ください。
なお、会社の経営状況に不安がある場合は、「相談事例5」をご参照ください。
相談事例3 降格に伴って賃金を下げられたケース
ご相談内容
会社から降格され、それを理由に賃金も下げられてしまいました。このような降格と賃金減額は法的に有効なのでしょうか?
弁護士の見解
降格も賃金減額も会社の自由にできるわけではありませんので、その有効性を争うことができるでしょう。
まず、降格自体が無効であれば、それに伴う賃金の減額も無効になりうることから、その降格の有効性を争うことが可能です。
また、降格を理由とした賃金減額とのことですが、降格や配置転換(異動)という人事措置と、契約内容として定められた賃金を減額することは別ものと考えられます。人事上の措置として降格させたとしても、当然に賃金減額が可能なわけではありません。賃金を減額するには、就業規則(賃金規程)や労働契約上の根拠が必要です。したがって、降格の有効性とは別に、賃金減額の法的根拠があるか等を検討し、減額が無効であることを主張することになります。
仮に降格に伴って賃金減額し得る場合であっても、その下げ幅があまりに大きいなど賃金減額の相当性が問題になる場合があります。
対応について
賃金減額の有効性は、交渉や訴訟、労働審判で争うことができます。
降格を理由とした賃金減額の場合、基本的には降格の有効性と賃金減額の有効性の両方を争うことになるでしょう。降格が人事権の濫用といえる場合は、無効となり、賃金も元に戻ります。
他方、仮に降格が有効である場合にも、賃金減額については無効と判断される可能性があります。
そもそも賃金減額に就業規則(賃金規程)や労働契約上の根拠がなければ、基本的には賃金減額は無効となるでしょうし、賃金減額に一応の根拠がある場合にも、例えば賃金減額の下げ幅が大きすぎることを理由に賃金減額が無効と判断される余地があります。
配置転換も同様です。たとえ、簡易な業務になったとしても、当然に賃金が下がるものではありません。
ぜひ諦めずにご相談ください。
相談事例4 退職金の金額が不当に下げられているケース
ご相談内容
退職金の金額が従前伝えられていた金額よりも低いのですが、退職金の金額を会社が勝手に引き下げることはできるのでしょうか?
弁護士の見解
まず、退職金の支給規程が存在するのか、その内容はどうなっているのかを確認する必要があります。
規程が存在するのであれば、会社はその規程に基づいて退職金を支給する義務があります。
他方で、特に規程が用意されていないものの、慣習として退職金が支給されている会社もあります。その場合には、過去の支給実績等と比較して支払われるべき金額の退職金を請求することが考えられます。
退職金の支給規程の内容が変更されているケースもあります。退職金の支給規程に定められていた退職金の具体的な金額や計算方法が労働者にとって不利益に変更されている場合は、このような規程の不利益変更の有効性を争い、不利益に変更される前の金額や計算方法で退職金を支払うよう会社に求めることになります。
対応について
退職金の計算方法は複雑な場合があり、規程があったとしても個人では理解が難しいかもしれません。弁護士が、勤続年数や在職中の賃金額、退職理由などをお聞きして、正しい退職金の金額を算出いたします。
退職金の支給規程が存在しない場合にも、過去の支給実績や他者と比べて不当に低い金額である場合には、その差額を請求する余地がありますので、ぜひご相談ください。
相談事例5 会社が倒産しそうなケース
ご相談内容
賃金が未払いなのですが、会社が倒産しそうだという噂を聞いています。このような場合には、未払いとなっている賃金はあきらめるしかないのでしょうか?
弁護士の見解と対応について
会社が倒産しそうな場合は、いかに賃金を確保できるかが勝負です。弁護士は会社の財産がなくなってしまう前に、回収することを目指します。
会社と交渉ができる状況であれば、未払いの賃金や退職金の金額を証明させ、残っている財産から賃金等の支払いをさせます(勝手に財産が処分されないようにすることも重要です)。
また、予め仮差押えなどをして財産を確保したり、上記の先取特権を利用して賃金等の回収をしたりすることも考えられます。
他方、すでに会社が法的な倒産手続を進めている場合には当該手続きの中で支払を受けることになりますが、すでに賃金の支払のための財産すら残っていない場合もあります。
また、法的な倒産手続をとっていなくても、事実上賃金を支払えない状態になっている、という場合もあります。
その場合には、一定の賃金の立替払いを受けられる制度があるので、その制度の利用を検討することになります(賃金の支払の確保等に関する法律)。
立替払いを受けられる要件や請求方法については、弁護士にお問い合わせください。