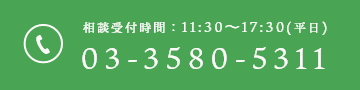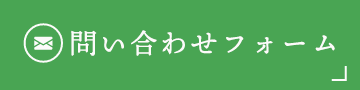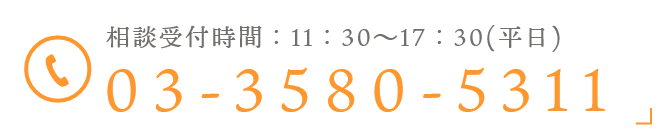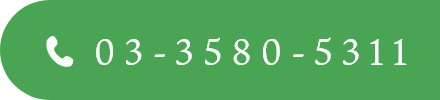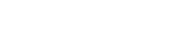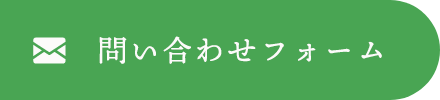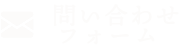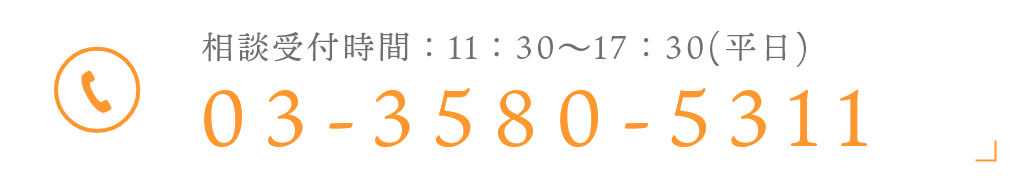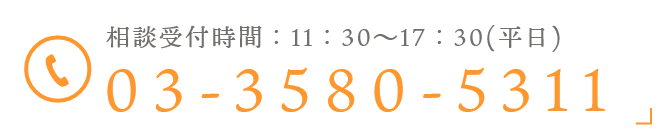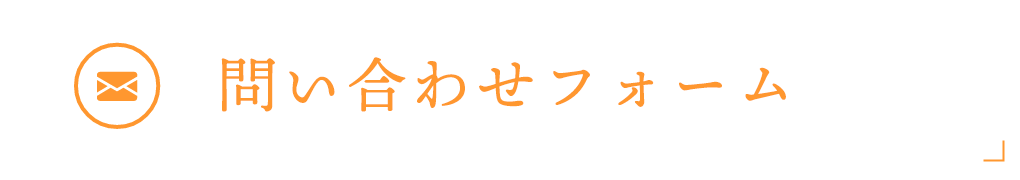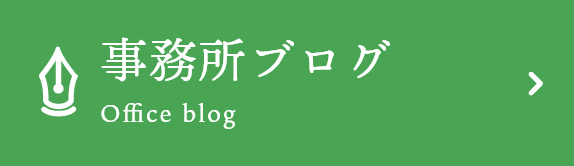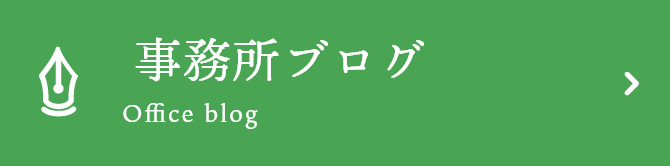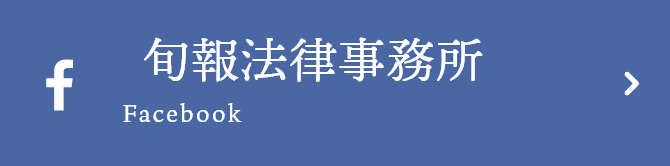その他の労働問題
その他の労働問題
懲戒処分や配転、降格などの他、不当労働行為などのご相談も承ります。会社から不当に損害賠償請求をされた場合や、最近非常に増えている、退職を希望しても辞めさせてもらえないケースなどにも対応します。
弁護士に相談するメリット

懲戒処分や配転、降格、使用者との団体交渉や不当労働行為の問題には多数の判例があり、これらに対処するには専門的知識や経験が必要です。
当事務所の弁護士には数多くの労働事件を取り扱った実績とノウハウがございますので、会社側の主張で泣き寝入りせず、まずは一度ご相談ください。
相談事例1 配転に関するケース
ご相談内容
私は、A社で入社以来20年間、印刷用機器の設計・開発に携わってきました。しかし、この春から、人員を削減する必要があると言われ、退職勧奨を受け、それを断ったところ、会社の倉庫に勤務場所を変更され、そこで、段ボール箱の整理をするように言われました。賃金も、手当がつかなくなるので、5万円下がると言われました。通勤時間も、これまでの1時間から、倍の2時間になるので、大変負担です。
このような配置転換に従う必要はあるのでしょうか。
弁護士の見解
会社が従業員に対して勤務場所や勤務内容の変更を命じることがあります。これを法的には「配置転換(配転)」といいます。使用者は、従業員に対して勤務場所や従事する業務を命じる裁量権を持っていると言われており、この配転命令権に基づいて、配転を命じます。
しかし、配転命令権も絶対ではなく、濫用は許されないとされています。使用者の配転命令権に基づく配転命令であっても、業務上の必要性の有無、労働者に与える不利益の程度、不当な動機・目的があるかどうかなどという点から、権利の濫用に該当しないかどうかを判断します。
対応について
A社による配転命令は、これまで入社以来20年間印刷用機器の設計・開発に携わってきた相談者を、倉庫での段ボール整理業務に従事させるもので、適材適所とは言い難く、業務上の必要性の存在は疑問です。
配転によって、賃金が5万円も減額されることになるし、通勤時間も倍増することになり、相談者に大きな不利益になるものです。
そして、この配転命令は、退職勧奨を断った直後になされたもので、これまでの業務とは大きく異なる畑違いの業務を行わせるものであることからすれば、労働者を退職に追い込むためにいわゆる「追い出し部屋」に追い込む目的でなされるもので、不当な動機・目的によるものです。
したがって、この配転命令は権利の濫用として無効と考えられます。
弁護士に依頼すれば、この配転命令の差し止めを求めて交渉を行い、場合によっては、配転命令の差し止めを求めて仮処分命令の申立てを行うことも考えられます。
なお、交渉中、仮処分の審理中に、配転命令の効力が発生してしまう場合には、その配転命令に従わなかった場合、それを業務命令違反として使用者が解雇をしてくるケースもあります。このような事態を避ける方法としては、通常は、配転命令に対しては異議を留めたうえで、不本意ではあるけれども配転命令に従ったうえで、法的紛争を続けるということが考えられます。
したがって、解決までの時間が長くなるようであれば、配転命令に対する異議を留め、一応は配転先に行って働くという措置も必要になります。
相談事例2 転職に関するケース
ご相談内容
私は、A社で電子部品の製造等の仕事をしていましたが、このたび、同業他社であるB社の社長に誘われ、待遇も良かったので、B社に転職しました。
すると、A社は、私が転職したことにより顧客を奪われたとして、私とB社に対し、多額の損害賠償を請求してきました。
確かに、A社の就業規則には、退職後2年間は同業他社への転職を禁じるという条項がありましたが、転職禁止に対しての代償措置は何もありませんでした。どうしたらいいでしょうか?
弁護士の見解
会社が従業員に対して、誓約書や就業規則等により退職後の競業(競合する企業への転職や開業)を禁止するのはよくあることです。
しかし、このような競業禁止措置は、従業員の職業選択の自由に対する重大な制約になりますから、無制限に認められるものではなく、競業禁止の内容・範囲が必要最小限のものであり、また、相当な代償措置が設けられているなど合理的なものでなければならないとされています。
対応について
A社の就業規則は、単に、同業他社への転職を2年間禁ずるとするだけのもので、その趣旨・目的が明らかではなく、内容・範囲も無制限で、代償措置もないというのですから、退職者の職業選択の自由を不当に制約するものとして無効と考えられます。
したがって、相談者が、A社を積極的に害する目的でA社の同僚を大量に引き抜いたとか、A社の営業秘密を盗用したなど事情がない限り、A社の損害賠償請求は認められないと考えられます。
また、退職時に会社から競業禁止の誓約書を求められることがあります。このような誓約書を書く義務はないので、サインしないようにしましょう。
こうした問題は訴訟に発展する可能性が高いので、早めに弁護士にご相談ください。
相談事例3 高齢者継続雇用に関するケース
ご相談内容
私は、2023年4月末に60歳を迎えて定年となりました。会社には、65歳までの継続雇用をうたった高齢者継続雇用制度があります。この制度では、60歳以降1年毎の有期雇用となり、賃金や労働時間も細かく決まっています。
私は、健康には何の問題もなく、継続雇用を希望しましたが、会社から拒否されてしまいました。どうしたらいいでしょうか?
弁護士の見解
高年齢者雇用安定法では、企業は、希望者全員につき65歳までの雇用を確保することが義務付けられています。現在、60歳で定年になった方については、従来あった継続雇用(再雇用)基準による選別は基本的にはできません。
ただし、企業は、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等、就業規則に定める解雇事由に該当する場合には、継続雇用しないことができるものとされています。
対応について
今回の場合、ここでいう勤務状況が著しく不良で就業規則上の解雇事由に当たるような事情があるかどうかが問題になります。そうした事情がない限り、会社は継続雇用の申出を拒否することはできず、継続雇用制度に基づく雇用関係が認められることになります。なお、勤務状況不良等の理由で解雇できる場合は、相当限定的に解されています。
したがって、ご相談者様について、継続雇用を拒否するのは、違法である可能性が高いと思われます。
会社に再考を求めても応じない場合は、労働審判や訴訟等で継続雇用を要求する必要があります。すぐ、弁護士にご相談ください。